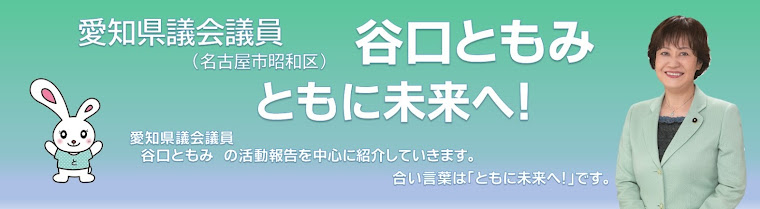2014年11月29日土曜日
2014年11月26日水曜日
晴天の下、グラウンドゴルフ大会
 写真で見ても、スゴイ晴天です。
写真で見ても、スゴイ晴天です。本当に良い天気の下、先週の日曜日は4回目となる「ともみ杯」のグラウンドゴルフでした。
私は始打式をさせていただきましたが、
 打つ格好からして・・・残念な感じです。
打つ格好からして・・・残念な感じです。90歳を超える方もご参加ですが、打った球の勢いのいいこと!
グラウンドゴルフの素晴らしさを毎回感じます。
皆さん、真剣にプレーしてみえ、
残念なスコアーに対しては、悔しさをしっかりと表わされます。
昨年、昭和区のチームが名古屋市の大会で良い成績を出されたとのこと。
悔しく思う気持ちで、強くなってみえるのですね。
2014年11月25日火曜日
広路小学校の学芸会で・・・
先週の土曜日、今期最後の昭和区小学校での学芸会は、広路小学校でした。
「ばかな。とんでもない嘘 うそ を言うわい。逃がした小鳥が帰って来るというのか。」
どこかで聞いたことがあるセリフ・・・と、聞きながら、会場に入っていくと・・・、
「走れメロス」でした!
私自身は中学校で、国語の教材として、授業をしていましたが、
メロスの葛藤を、二手に分かれて表現したり、
沈む太陽をスポットライトで表現したり、
とても工夫されているなぁと、感心しながら劇を拝見しました。
子どもたちは、せりふとして暗記した文学作品の文章が心に残って、
これからの心の財産になると思うと、それも素敵です。
「ばかな。とんでもない嘘 うそ を言うわい。逃がした小鳥が帰って来るというのか。」
どこかで聞いたことがあるセリフ・・・と、聞きながら、会場に入っていくと・・・、
「走れメロス」でした!
私自身は中学校で、国語の教材として、授業をしていましたが、
メロスの葛藤を、二手に分かれて表現したり、
沈む太陽をスポットライトで表現したり、
とても工夫されているなぁと、感心しながら劇を拝見しました。
子どもたちは、せりふとして暗記した文学作品の文章が心に残って、
これからの心の財産になると思うと、それも素敵です。
2014年11月16日日曜日
小学校作品展&学芸会(吹上、御器所、村雲、白金、八事、滝川)&松栄コミセン
先週、今週と昭和区の小学校の作品展や学芸会に伺いました。
(残念ながら、全ての学校に・・・という訳にはいきませんでしたが)
(残念ながら、全ての学校に・・・という訳にはいきませんでしたが)
子どもたちのきらきら感性の作品が楽しい!
大きな声で頑張る子どもたちが可愛らしい!
大きな声で頑張る子どもたちが可愛らしい!

2014年11月14日金曜日
バイオ&医療戦略、平和、水道事業の調査へ
バイオと医療、平和と水道事業、と、一見バラバラな観点に見える調査項目ですが、
 どれも愛知県にとっても大きな課題であり、
どれも愛知県にとっても大きな課題であり、
大阪府と広島県で調査させていただきました。
調査項目のタイトルは、
「大阪バイオ戦略」
「大阪府市医療戦略会議 提言」
「国際平和拠点ひろしま構想」
「広島県営水道における公民連携の取組」です。
 背景の違いがあるので、一概に良いとか悪いとかの問題ではありませんが、
背景の違いがあるので、一概に良いとか悪いとかの問題ではありませんが、
大阪府や広島県では勢いある取り組みがされていました。
参考にさせていただけることがいっぱいです。
 どれも愛知県にとっても大きな課題であり、
どれも愛知県にとっても大きな課題であり、大阪府と広島県で調査させていただきました。
調査項目のタイトルは、
「大阪バイオ戦略」
「大阪府市医療戦略会議 提言」
「国際平和拠点ひろしま構想」
「広島県営水道における公民連携の取組」です。
 背景の違いがあるので、一概に良いとか悪いとかの問題ではありませんが、
背景の違いがあるので、一概に良いとか悪いとかの問題ではありませんが、大阪府や広島県では勢いある取り組みがされていました。
参考にさせていただけることがいっぱいです。
2014年11月11日火曜日
ESDユネスコ世界会議 → グリーン社会へ
2014年11月10日月曜日
県外調査~「生活支援ロボット安全検証センター」と「株式会社 みらい」
先週、産業振興・雇用対策特別委員会の県外調査がありました。

つくば市の「生活支援ロボット安全検証センター」では、
介護に携わる方々へのサポートをするための「ロボット」の安全性を検証することについてのさまざまなお話を伺いました。
「ロボット」って、定義はないそうです。
道具っぽいものから、人間に近い動きをする精密な機器まで、海外との競争の中で開発を進めていくことの大変さを垣間見ました。
 また、欧州、米国、日本で、「安全」に対する考え方は随分と違うようです。
また、欧州、米国、日本で、「安全」に対する考え方は随分と違うようです。
完全な安全はないということ、また企業などは社会的責任をきちんと果たしているかといことが大事で、どう注意してものを扱うのかという観点をもつ、大人な雰囲気の欧州の考え方と、日本は生活支援ロボットの開発において、競争していかなければなりませんが、
以前から、医療・福祉関連について、議会でも質問している私にとっては、とても興味深い調査でした。


柏市の「株式会社 みらい」では、人工光型植物工場で、
一日1万株ものレタスを栽培。
工場の規模を大きくし、さまざまな工夫を重ねることで、
採算が合わないと言われていた業界に革命的なことを起こしたのです。
でも、工場を作ればいいというものでは、ない、ということは、お話の中にもたくさん出てきました。
ソフト=作り方が大事なのだそうです。
高齢化で農業の担い手不足が進む中の救世主になりえそうです。

つくば市の「生活支援ロボット安全検証センター」では、
介護に携わる方々へのサポートをするための「ロボット」の安全性を検証することについてのさまざまなお話を伺いました。
「ロボット」って、定義はないそうです。
道具っぽいものから、人間に近い動きをする精密な機器まで、海外との競争の中で開発を進めていくことの大変さを垣間見ました。
 また、欧州、米国、日本で、「安全」に対する考え方は随分と違うようです。
また、欧州、米国、日本で、「安全」に対する考え方は随分と違うようです。完全な安全はないということ、また企業などは社会的責任をきちんと果たしているかといことが大事で、どう注意してものを扱うのかという観点をもつ、大人な雰囲気の欧州の考え方と、日本は生活支援ロボットの開発において、競争していかなければなりませんが、
以前から、医療・福祉関連について、議会でも質問している私にとっては、とても興味深い調査でした。


柏市の「株式会社 みらい」では、人工光型植物工場で、
一日1万株ものレタスを栽培。
工場の規模を大きくし、さまざまな工夫を重ねることで、
採算が合わないと言われていた業界に革命的なことを起こしたのです。
でも、工場を作ればいいというものでは、ない、ということは、お話の中にもたくさん出てきました。
ソフト=作り方が大事なのだそうです。
高齢化で農業の担い手不足が進む中の救世主になりえそうです。
登録:
コメント (Atom)